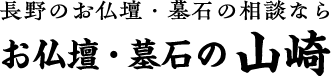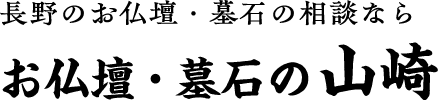長野のお仏壇コラム
「もうお墓はいらない…」、お墓を手放す前に考えたいこと
こんな人におすすめ
- お墓を持つべきかどうか悩んでいる方
- お墓じまいを考えている方
- 死後のことを自分で決めたいと考える終活中の方
「お墓じまいを考えている…」ここ数年、そんな声を耳にすることが増えました。
散骨、樹木葬、手元供養。供養のかたちが多様になり、時代はモノを持たないことに価値を置くようになりました。
身軽で自由な生き方が尊ばれるなかで、長期的な維持や場所を必要とするお墓は、時に重たい存在に感じられてしまうのかもしれません。
その一方で、私は仏壇屋という仕事を通して、たくさんの“お墓にまつわる思い”と出会ってきました。
そこには、決してモノとしての価値だけでは語れないものがあります。
「会いに行ける場所があって良かった」
「お墓があったから、家族の関係がつながった」
今回は、そんな声を通して、お墓という存在の意味を一緒に見つめ直せたらと思います。
故人との対話の場としてのお墓
お客様がお墓を持たない選択をする背景には、いくつかの理由があります。
たとえば経済的な理由です。
お墓を建てる費用や維持にかかる管理費、お墓参りにかける時間や体力の問題など。
あるいは、昔のように宗教的な義務感が薄れ、「供養=形式」だと感じている方も少なくありません。
私たちの暮らしや考え方が変わってきたのなら、供養のかたちが変わるのも自然なことだと思います。
そんな時代であっても、墓前に立って手を合わせると、ふと故人との思い出がよみがえってくる。そんな経験をされた方も多いのではないでしょうか。
お墓は語りませんが、そこに想いを差し向ける時間と場所があることで、故人との対話ができるのです。
お墓が持つ3つの役割
お墓には3つの役割があると、私は思います。
ひとつは、記憶を継ぐこと。
墓石に刻まれた名前や言葉は、その人の人生を静かに物語ります。
そこには、家族が知らなかった一面や、残したい思いが宿っているはずです。
もうひとつは、心を区切ること。
お墓参りの習慣は、喪失を受け止める節目といえます。
時間が経つほど忘れるのではなく、折り合いをつけていく営みとしての意味があるのです。
そして最後は、祈りを続けること。
会いに行ける場所があることで、人は人生の中で何度でも故人とのつながりを感じ直せるのだと思います。
この記事のまとめ
もうお墓はいらない――。
そう思った方にこそ、一度立ち止まって、「どんな形なら、心に残るだろう?」と考えてみてほしいのです。
納骨堂、永代供養墓、自然葬…。いまは墓石の形も、納骨の方法も、柔軟に選べる時代です。
「供養とはなにか」を一緒に考えながら、その方らしい答えを見つけるお手伝いをする。
それが私たちの役目です。
お墓とは、命の終わりに立てるものではなく、誰かを想い、未来につなげる「対話の始まり」なのかもしれません。
供養の形が変わっていっても、そこに込められた「誰かを想う気持ち」だけは、いつの時代も変わらないものです。
当店ではお墓を販売するというよりも、お客様の心にそっと寄り添う姿勢を大切にしています。
お墓を持つかどうか悩んでいるという方でも、お気軽にご相談ください。