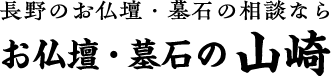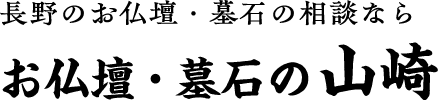長野のお仏壇コラム
供養に欠かせない「ろうそく」の種類と選び方のポイント
こんな人におすすめ
- ろうそくの購入を考えている方
- ろうそくの種類や特徴を知りたい方
- お店での選び方を知りたい方
前回の記事では、「線香」について解説しました。
線香と同様に、ご先祖様への供養に欠かせないものとして、「ろうそく」があります。
ろうそくは、お仏壇の灯明として使用される大切な仏具のひとつで、火を灯すことで心を静め、祈りの場をより神聖なものにしてくれます。
本記事では、ろうそくの種類と選び方について詳しく解説します。

ろうそくの歴史
日本では仏教の伝来とともにろうそくの歴史が始まったとされています。
奈良・平安時代のろうそくの原料は蜜ろうで、唐から輸入されたものを使っていました。
遣唐使船が廃止されると蜜ろうの輸入が途絶え、代わりに松脂を使ったろうそくが登場します。
現在でいうところの和ろうそくが誕生したのは、室町時代後期です。
明治時代になると、ヨーロッパからパラフィンを使った洋ろうそくの製法が伝わり、庶民の間に広まるようになりました。
ろうそくの種類と特徴
ろうそくは、大きく分けて「和ろうそく」と「洋ろうそく」の二種類があります。
また、形状は、一般的な「棒状のもの」と上部が広がった「いかり型」のものに分けられます。
①和ろうそく
ハゼの実などの植物性の原料を使用し、い草と和紙で作られた灯芯を持つものを和ろうそくと呼びます。
伝統工芸品としても知られ、自然な風合いと優しい炎が特徴です。
高価なため、法事や月命日などの特別な日に使われる方が多いです。
また、和ろうそくの一種に「絵ろうそく」があります。
これは和ろうそくに花などの模様をあしらったもので、生花の代わりに火を灯さずにお仏壇に飾ることもあります。
②洋ろうそく
一般的に市販されているものは、石油から精製されるパラフィン製のろうそくです。
比較的安価で入手しやすいことから、主に日常用として使われています。
長さはさまざまで、短いものでは2cmくらいから、30cm以上の長いものまであります。
長時間燃える大型のものは、お盆や法要などで使用されることが多いです。
③LEDろうそく
近年では、火を使わない電池式のLEDろうそくも使われています。
お年寄りや小さなお子様がいる家庭でも安心して使える点が魅力です。
この記事のまとめ
ろうそくを灯すことは、華と香と並ぶ供養の基本です。
本記事をご参考に、使用する場面に応じて最適なものをお選びいただけたらと思います。
華やかな絵ろうそくは、ご進物にも最適ですので、ぜひ当店でお手に取ってお選びください。