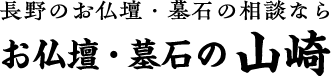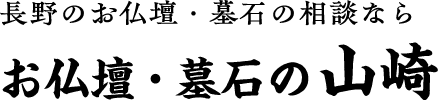長野のお仏壇コラム
各宗派の戒名の特徴|位牌を作る際に注意したいこと
こんな人におすすめ
- これから位牌をお求めの方
- 戒名の意味や構成要素を知りたい方
- 宗派ごとの戒名の違いを知りたい方
以前のコラムでは、位牌について解説しました。
位牌とは故人の霊魂を祀るための仏具で、戒名、没年月日、俗名、享年を記載したものです。
今回は、この中の「戒名(かいみょう)」について、その意味や構成要素、宗派ごとの違いについて詳しく解説します。

戒名とは?
戒名とは、元来仏教の教えを学び、戒律を守ることを約束した証として与えられる名前のことです。
かつては、出家した証として生前に与えられるものでしたが、現在では亡くなってから戒名を受けることが一般的になりました。
これは、仏の世界には俗名のままでは行けないと考えられているためです。
通常、戒名は菩提寺(先祖代々のお墓があるお寺)の住職に、故人の生前の名前や人柄、功績などを考慮して付けてもらいます。
ただし、菩提寺がない方の場合は、葬儀社から紹介された寺院に依頼することもあります。
また、公営墓地などの宗旨・宗派不問の霊園に納骨する場合や、永代供養墓などの場合は、必ずしも戒名は必要ありません。
納骨先によって戒名の必要の有無が変わるため、事前に確認しておく必要があります。
戒名を授かるタイミングは、亡くなった後、お通夜が始まるまでの間が一般的ですが、「生前戒名」という方法で、生前に戒名を授かる場合もあります。
戒名の構成要素
戒名は、一般的には6〜9文字程度の場合が多く、通常、以下の4つの要素で構成されます。
1. 院号(いんごう)・院殿号(いんでんごう)
戒名の一番上に付く位で、菩提寺との関わりが深い人や社会的な貢献度が高い人だけに与えられる称号です。
例えば、「○○院」「○○院殿」のように記されます。
2. 道号(どうごう)
元々は悟りを開いた僧侶に与えられる称号でしたが、現在では、故人の人柄や趣味、場所などを表すものとして用いられています。
人柄や趣味を表すものでは「光」や「翁」、場所などを表すものでは「山」「海」などが多く見られます。
3. 戒名(かいみょう)
仏弟子としての新しい名前で、俗名(生前の名前)や仏様の名前、先祖代々受け継いできた文字などから取った2文字が用いられます。
4. 位号(いごう)
戒名の一番下に付く位で、性別や年齢、社会的地位を表す称号として用いられます。
例えば、成人男性の場合は「居士(こじ)」、成人女性の場合は「大姉(たいし)」などが用いられます。
宗派ごとの戒名の違い
戒名は、各宗派によって付け方や特徴が異なります。
また、寺院によっても梵字の記載の有無などが変わる場合があります。
●浄土宗
戒名の一番上に阿弥陀仏を表す梵字(※)が入ることがあります。
また、道号の代わりに「誉号(よごう)」が用いられ、戒名の上に「誉」の文字が入ります。
例:「(※)○○院誉○○居士」
●浄土真宗
浄土真宗では、戒名ではなく「法名(ほうみょう)」と呼び、「釋(しゃく)」の文字が入ります。
道号や位号は付かず、男性は3文字、女性は4文字で表すことが多いです。
例:「釋○○」「釋尼○○」
●真言宗
通常、戒名の一番上に大日如来を表す梵字(※)が付きますが、梵字の有無は寺院によって変わる場合があります。
例:「(※)○○院○○」
●日蓮宗
戒名ではなく「法名(法号)」が用いられ、男性は「日」、女性は「妙」の文字が入ります。
例:「○○院○日○居士」「○○院○妙○大姉」
●曹洞宗・臨済宗
白木位牌には、戒名の一番上に「新帰元(しんきげん)」の文字が入ることがありますが、本位牌には記載しません。
例:「○○院○○大姉」「○○院○○大居士」
●天台宗
戒名の一番上に大日如来を表す梵字(※)が付くことがありますが、その有無は寺院によって変わる場合があります。
例:「(※)○○院○○大姉」。
このように戒名は、亡くなられた方の年齢や性別、社会的地位など、さまざまな要素から構成されています。
また、宗派や寺院によっても入れる文字が異なるため、お位牌を作る際には注意が必要です。
そのため、事前に寺院から指示を受けたうえでお位牌を作成されることをおすすめします。
当店では、お位牌や墓石の戒名の文字入れ・文字彫りも承っています。
お位牌のことでご不明な点などありましたら、お気軽に当店にご相談ください。