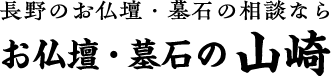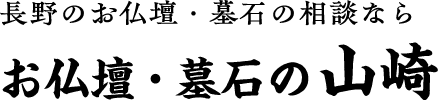長野のお仏壇コラム
長野県のお盆|お盆用品やお供え物について知る
こんな人におすすめ
- お盆用品の意味を知りたい方
- 地域の風習に合わせた準備をしたい方
- お盆の準備が初めての方
こんにちは。長野市でお仏壇・墓石の専門店を営んでおります山崎です。
この時期になると、お盆に向けて盆提灯やお線香などを求めに来店されるお客様が多くなります。
今回は、お盆を迎えるにあたって「何を準備すればいいのか分からない」「どんなものを選べばいいのか迷う」という方のために、お盆用品の種類とそれぞれの役割について、わかりやすく解説します。

お盆の意義とお盆用品の役割
お盆は、ご先祖様の霊がこの世に戻って来るとされる、日本の大切な伝統行事です。
長野県では毎年8月13日から16日頃にかけて行われるのが一般的で、家族が集まり、お仏壇やお墓をきれいに整え、ご先祖様をお迎えします。
この期間に使うお盆用品は、ご先祖様をお迎えし、感謝の気持ちを伝えるための大切な道具です。
単なる飾りではなく、それぞれに意味や役割があり、心を込めて準備することで、より丁寧な供養につながります。
お盆用品やお供え物の種類
お盆用品にはさまざまなものがありますが、ここでは代表的なものをご紹介します。
その中には、全国的にはあまり見られない長野県の地域性が見られるものもあります。
精霊棚(しょうりょうだな)
ご先祖様をお迎えするための祭壇で、盆棚(ぼんだな)とも呼ばれます。お仏壇とは別に設けることが多く、お位牌やお供え物を飾ります。
盆提灯(ぼんちょうちん)
ご先祖様が迷わず帰ってこられるように灯すもので、スタンドで吊るすタイプの「吊り提灯」と直置きタイプの「置き提灯」があります。
>長野県の盆提灯について詳しく知る
精霊馬(しょうりょううま)
キュウリで作った馬とナスで作った牛。馬は早く帰ってきてもらうため、牛はゆっくり戻っていただくための乗り物とされています。
おがら(麻の茎)
迎え火・送り火の道具で、焙烙(ほうろく)で焚いて、ご先祖様の道しるべとします。長野県では、北信地域では「かんば(白樺の皮)」、佐久地域では「わら」を焼くなど、地域によって風習が異なります。
お供え物
季節の果物、天ぷら、そうめん、故人の好物などをお供えするのが一般的です。特に決まりはなく、長野県では、おやきや天ぷらまんじゅう、えご(海藻)などをお供えする家庭もあります。
お墓参り用品
線香、ろうそく、盆花など、お盆用に特別なものをお求めになる方もいらっしゃいます。
>お線香について詳しく知る
>ろうそくについて詳しく知る
この記事のまとめ
お盆は、ご先祖様と心を通わせる大切な時間です。
お盆用品は、その気持ちを形にするための道具。意味を知り、丁寧に選ぶことで、より深い供養ができるはずです。
当店では、盆提灯をはじめ、線香やろうそく、造花など、各種お盆用品を取り揃えております。
初めての方にもわかりやすくご案内しますので、どうぞお気軽にご相談ください。