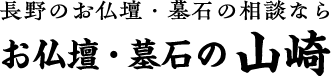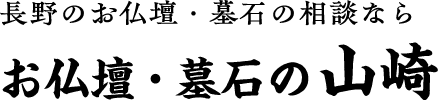長野のお仏壇コラム
仏事の流れを解説|通夜から年忌法要まで
こんな人におすすめ
- 仏事の流れを知りたい方
- 位牌や仏壇がいつまでに必要なのかを知りたい方
- 仏壇や仏具の購入を検討している方
当店をご利用いただくタイミングとして多いのは、ご家族が亡くなられて、お仏壇や仏具をお求めになられる場合です。
最近では、葬儀屋さんからの案内のためか、葬儀が終ると早いタイミングで来店される傾向にあります。
お仏壇や仏具を揃えるタイミングとして、仏事の流れを理解しておくと安心です。
今回は、各仏事の内容やその流れについて、分かりやすく解説します。

仏事の基本的な流れ
仏事は、故人の冥福を祈り、供養するための仏教の儀式で、「法事(ほうじ)」や「法要(ほうよう)」とも呼ばれます。
通常は、下記の流れで行われます。
1. 通夜
亡くなった翌日の夜に、遺族や近親者が自宅に集まり、故人と過ごす儀式です。
↓
2. 葬儀・告別式
故人を送り出すための儀式で、一般的には通夜の翌日に、斎場や寺院などで行います。
通常は、葬儀・告別式を同じタイミングで行います。
↓
3. 初七日(しょなのか)法要
亡くなってから7日目に行う法要で、遺族や近親者が集まり、僧侶による読経と参列者による焼香で、故人のあらたな旅路を祈ります。
その後、二七日(14日目)、三七日(21日目)、四七日(28日目)、五七日(35日目)、六七日(42日目)、七七日(49日目)と、7日ごとに計7回の法要を行います。
↓
4. 四十九日(しじゅうくにち)法要
亡くなってから49日目に行う法要で、故人の来世が決まる日とされています。
これをもって忌明けとなり、白木位牌を本位牌に変えます。
同日に、僧侶による魂入れ(たましいいれ)を行うことが一般的です。
↓
5. 一周忌法要
亡くなった日の翌年の祥月命日(亡くなった月日)に行う法要です。
故人を偲ぶため、親族や友人が集まり、お墓参りや会食を行います。
祥月命日が平日の場合は、その前の土日に行うことが一般的です。
↓
6. 三回忌法要
亡くなってから2年目の祥月命日に行う法要です。
一周忌と同様に行われますが、規模はやや小さくなることが多いです。
↓
7. 七回忌以降の法要
七回忌(命日から満6年目)、十三回忌(命日から満12年目)、十七回忌(命日から満16年目)、二十三回忌(命日から満22年目)、二十七回忌(命日から満26年目)、三十三回忌(命日から満32年目)と続きます。
一般的には、三十三回忌をもって一区切りとすることが多いです。
通夜から年忌法要まで、仏事の流れをご紹介しました。
お仏壇や仏具は、四十九日法要までにご用意される方が多いですが、この日までに揃えなければならないという決まりがあるわけではありません。
ただし、早めに準備を進めることで、心の余裕を持って故人を偲ぶことができます。
また、本位牌については、四十九日法要までに用意していただく必要があります。
お位牌の作成には、通常1、2週間かかるため、余裕を持ってお求めになることをおすすめします。
当店でもお位牌の作成を承っておりますので、お仏壇や墓石と併せてご依頼ください。